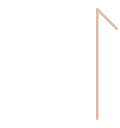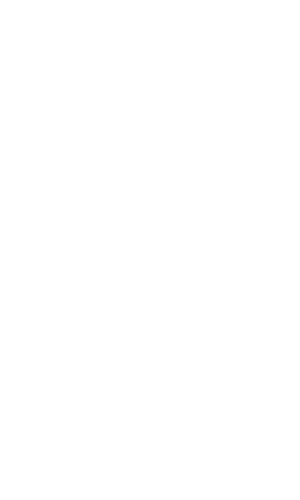
美しい仕事がしたいと願って
わたしの仕事は、「詩のソムリエ」だ。
「よい詩をあらゆる手段で人に届けること」を仕事にしている。
2018年に本職のかたわらはじめたけど、だんだん仕事らしくなってきたし、開業届も出したし、胸をはって名乗ろうと思う。
独立前は、とある会社で高校生のキャリア教育教材をつくっていたので、《仕事》というのは大きな関心事であり続けている。
生活の大きな領域を占める「仕事」は、「どう生きるか」と同義だ。
自分が仕事人として、いつも心から願っているのは、「美しい仕事がしたい」ということ。
では、”美しい仕事”ってなんだろう?
納期やコンプライアンス(法令)を遵守するとか、心配りとか、いろいろあると思う。ぜんぶ大事だと思うけど、わたしなりに定義するのであれば…
「人に生きる力をあたえる仕事」が美しい仕事だと思う。
ここでひとつ、美しい仕事について考えてみたい。
病院食の紅葉麩が、わたしを生かす
ふつうに生きていると、大人の美しい仕事にでくわす機会はそんなに多くない。わたしもまた、なりふり構わず部活に塾に…とせまい世界のなかで忙しく生きる子どもの一人だった。
そんなわたしが幸いにも「美しい仕事」に出会ったのは高3のとき。
17歳、いのちの輝き盛りの夏に、わたしは病室にいた。
肺胞が破れていて、外の空気を一切吸わずに何週間か過ごしていた。
あの夏はとくに暑く、外の濃密な空気を吸おうものなら死んでしまうんじゃないか…と本気で思っていた。
体のいたるところがズタズタで、ぼうっとベッドのうえで過ごす日々。
知覚もかなり衰えていたと思う。
高3の夏。
同級生たちが未来に向かってエンジンを全開にしているとき、わたしはどこへも進めなかった。
「学校暑いから(当時エアコンがなかった)、涼しくなったら学校くればいいよぉ」
お見舞いに来てくれたギャルが秋服で言うのを、ぼんやりうなずく。学校に戻れるんだろうか…と思いながら。
そんなある日、食事に”紅葉麩”が出た。
煮物のなかの、紅葉麩のあかが目を奪った。
(もう秋が来るんだ…)
目をあげよ物想うなかれ秋ぞ立つ、いざみずからを新しくせよ(若山牧水)
季節が変わる。
細胞が生まれ変わる。
もう、息もすえる。
寝たきりだったので体力が異様に衰えていて、食事は一時間かけて、汗をぜいぜいかきながら食べていた。それでも懸命に食べた。
そして今、わたしは元気で、詩のレシピを考案して発信するようになった。
あのとき病院食をつくってくれた方に、ついぞお礼を言えないままだ。お顔を拝見することもできなかったけど、きっと、入院患者たちがすこしでも季節を感じられるように心を砕いてくださったんだと思う。
彼/彼女の仕事は美しい。
その心が、いまも私を生かしている。
はんぶんの寿司が、彼を生かす
時は流れて25歳になったころ、鎌倉の小花寿司さんという老舗にお寿司を食べにいった。カウンターに、おじいさんが一人。
そのお寿司ははんぶんに切ってあった。
「この人ね、胃が半分ないのよ」
大将が苦笑する。「病院から抜け出してきたの。困った人だねもう」
そんなことを言いながら、トロ、カンパチ、軍艦巻…すべてのお寿司をきれいに半分にして出す。
当の、手術で胃を切除した「脱獄犯」はじつに旨そうに寿司を口にし、「あんたも食べるか」と言って、生牡蠣をおごってくれた。彼はほんとうに幸せそうだった。牡蠣は今まで食べたことがないほどおいしかった。
かの、夭折した美しい夏目雅子さんが通っていたお寿司屋さんだと知ったのはすこしあとになってからだった。やさしい困り顔の大将。病気で亡くなった彼女に、このお寿司屋さんがあってよかったと思う。
美しい仕事は人を生かす。それが、ほんの数ミリだったとしても。
ことばが、人を生かす
ことばもまた、人を生かす力があると思う。
わたしがもっとも尊敬することばの使い手は、詩人ではなく、とある医師だ。
徳永進(とくなが・すすむ)医師は、鳥取市内でホスピスケアのある「野の花診療所」をはじめた。その日々を記した『野の花の病院案内』という本で強く心に残ったのが「あさって」という言葉の使い方だ。
余命いくばくもない患者が「先生、明日自分は死にますか?」と聞く。すると、「そうだねぇ、あさってじゃないかなぁ」と答える。患者は「そうですか、あさってですか」と安心して目をとじる…。
「あさって」という日本語は、the day after tomorrowという英語の機械性とちがって、ぽかーんと放り投げられたようなふくらみのある、空間の「向こうがわ」のことばだという。
死に臨むひとりにとって、迫りくる「明日」ではなく、ほわんと向こう側に広がる「あさって」だということが、どれだけ救いになるだろう。
医者の仕事はもちろん技術面が大事なのは言うまでもないけれど、徳永先生の仕事の、なんと美しいことか。その仕事っぷりには心打たれる。
詩は人を世界と共に生かすためにある
さて、詩は一般に「役に立たない」ものと思われている。それは、不況で即戦力を求める現代社会がそうしているのではなく、「詩を作るより田を作れ」という身も蓋もないことわざもあるくらいに、昔っからそうだ。
そもそも、詩を「役に立つ・立たない」の二元論で語りたくないけれど、日本の代表的詩人である谷川俊太郎さんは、エッセーのなかでこんなことを言っている。
詩は彼を世界と共に生かすためにあるのだ。そして詩人は、ひとつの死体の前で、〈私も彼を生かした、丁度彼が私を生かしてくれたと同じように。〉といえるようにならねばならぬ。 (「世界へ!」1959)
詩は誰かを生かすためにある。
20代後半の俊太郎さんの気合が入りまくっていて、胸にしみる言葉だ。
この3年前に出した「絵本」(1956)には、「生かす」と第された詩がある。
六月の百合の花が私を生かす
死んだ魚が生かす
雨に濡れた仔犬が
その日の夕焼が私を生かす
生かす
忘れられぬ記憶が生かす
死神が私を生かす
生かす
ふとふりむいた一つの顔が私を生かす※一部抜粋
そうだ、詩は誰かを生かすためにあるのだ。
わたしはそれを信じている。
だから詩のソムリエをやる。たぶん一生やり続ける。
わたしもまた、美しい仕事をしたいと思う。
正しく清くはたらくひとはひとつの大きな芸術を時間のうしろにつくるのです。
「マリヴロンと少女」 宮沢賢治
おまへは世の中へでてもつと世間をみて来なければならない
世の中でおまへのしなければならない仕事は沢山ある
小鳥を森へかへすのだ
「断章4」山村暮鳥